“ふくしま式200字メソッド”で「書く力」は驚くほど伸びる! 福嶋隆史
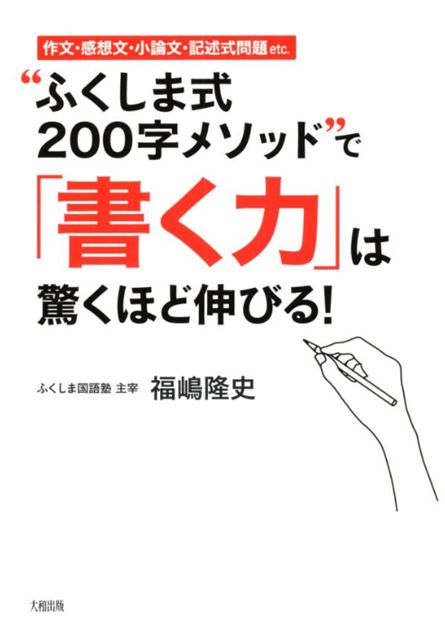
この本は、国語塾を経営されている福嶋隆史(ふくしまたかし)さんが「本当の国語力」の身につけ方について書く力に重点を置いて書かれた本になります。
対象は小学生を持つ親御さんに向けに、我が子に国語力を指導できるように書かれた本ですが、中学生、高校生、大人までも、参考になる本だと思います。
中学生以上になると、自分自身で読んで勉強できるないようではないかと思います。
福嶋隆史さんが書いた本はどれも「言いかえる力」、「くらべる力」、「たどる力」について説かれています。
この3つの基本的な力については「「本当の国語力」が驚くほど伸びる本―偏差値20アップは当たり前! 福嶋隆史」を参照してください。
このシンプルな3つの力を「書く力」に応用し、理論的思考の「型」を追及していくという内容になっています。
スポンサーリンク
以下、この本の内容紹介です。
どう書き出していいか分からず、ペンを持ったまま固まってしまう。
その理由は大きく分けて2つあります。
・「書く内容」が浮かばないということ。
・「書く方法」を持っていないということ。
「何を」「どう」書くのか。内容と方法。
さて、このうち、優先的に解決すべきは、どちらでしょうか。
多くの人はここで間違えます。「内容(何を書くか)」を重視してしまうのです。
あの場面の話をかけばいいんじゃない。などと内容についてアドバイスしてしまいます。その場では分かったような気になりますが、その場限りです。
次に別の内容を書くと手も足も出ません。こんなことを繰り返しても「書く力」は育ちません。永遠に。
では、どうすればいいのか。答えは簡単「内容」ではなく「形式」優先で「どう書くか」にこだわることこそが大切です。
これは、書くための方法、書くための技術、書くための「型」を意味します。
「型」があればこそ、「内容」が生み出されるのです。
3つの力を使った型
————————————————————————————-
「ア」は、「1」(な)ため、「A」である。(「言いかえる力」を使った文)
————————————————————————————-
↑
対比関係「比べる力」
↓
————————————————————————————-
しかし、「イ」は、「2」(な)ため、「B」である。(「言いかえる力」を使った文)
————————————————————————————-
↑
因果関係「たどる力」
↓
————————————————————————————-
だから、「ア」よりも「イ」のほうが「C」であるといえる。
————————————————————————————-
・「言いかえる力」:同等関係を整理する力
・「くらべる力」:対比関係を整理する力
・「たどる力」:因果関係を整理する力
「対比関係」、「なにか」を否定して「なにかを」を肯定する、これこそが「型」の心臓部です。
ほとんどの文はこの「型」で書かれています。この「型」さえあればほとんどの文章が書けます。
対比こそが主張を支えています。
人は「対比と選択」を繰り返しています。
そして、「天秤に乗せたような対比」「鏡に写したようなきれいな対比」で書くことが重要です、要するに、型どおりに書くということです。
慣れないうちは「型」を崩してはいけません。
多くの人は、「自由を与えれば、人は自由になる」と思い込んでいます。
自由を与えれば与えるほど、子どもは不自由になります。
自由を限定すればするほど、子どもは自由になります。
型は個性を奪いません。
型こそが、個性を伸ばします。
この「型」で書き方を「限定」するからこそ書き手は「自由」になれるのです。
スポンサーリンク
たとえば、水泳。
クロールにも、平泳にも、背泳ぎにも、バタフライにも、それぞれ、最善の「泳ぎ方」「泳ぐ技術」があります。いわば、泳ぎの「型」です。
この型を身につけないまま、海に子どもを放り出してみたらどうなりますか?
当然泳げません、溺れるでしょう。そしてどこへも行けません。これほど不自由なことはありません。
一方、型を身に付けていれば、泳げます。自由に泳げます。そして、あの島まで、行きたい場所へ、どこでも自由にたどり着けます。
かといって、中途半端な型では、役に立ちません。
水泳のどんな種目にも、いえ、水泳だけではなく、どんな競技にも、最善の「型」があります。
だから、同じ動きになるわけです。
それどころか、あらゆる方法という方法に「ベストの型」があるのではないでしょうか。
調理でも、音楽でも、建築物でもそこには洗練された型があります。
芸術は簡単にはまねできませんが、技術、すなわち「型」は容易に真似できます。
そして、「型」を指定することで、完璧ではないにしろ、優れた文章が書けるようになります。
すなわ「型が内容を呼び込む」ということです。
まずは「型」に沿って骨組みをつくり肉付けして、文字数を調整していきます。
観点を増やせばおのずと文章は長くなり、200字が400字、800字になっていきます。
文章のレベルは「対比の観点」で決まる!
ハイレベルな観点の条件は3つ
1、客観性が高いこと:10人中8人が納得する内容を意味します。
2、独自性が高いこと:10人中2人以下しか思いつかないような内容を意味します。
3、普遍性が高いこと:世の中のさまざまなことがらに広く当てはまるような観点を意味します。
対比の観点レベルを高める方法
静的観点から動的観点へ
たとえば、自転車と三輪車を比べるとき、静的観点では「タイヤの数」や「タイヤの大きさ」が真っ先に浮かびます。誰でもが知っている常識レベルです。
なぜなら、視覚に頼り過ぎているからです。
そういった、観点を脱するには、「動き」を想像することです。
使用しているイメージできれば、「スピードの違い」「一こぎで走れる距離の違い」といった相違点が浮かび始めます。
そして、最終的には「用途の違い(自転車は移動手段であり、三輪車は遊具であること)」といったレベルにまで到達できます。
このように、多くの人が知ってはいるが、だれも表現できなかったことを表現できた時、そこに独自性が生まれるのです。
言いかえれば、「有形の観点から無形の観点へ」ということです。
たとえば、青空と曇り空の違いを、「雲の有無」「傘を持って行く必要性」などとぜず、「前向きな気持ちになりやすいかどうか」とします。
形ある雲や傘ではなく、形なき「気持ち」に目を向ける必要があります。
これらの考え方は「モノ」ではなく、「心」に目を向けるということでもあります。
最後に、
あらゆる芸事に当てはまる「守・破・離」という考え方があります。
とにかく、まずは「型どおり」に書き、型を完全にマスターしてから、
逆説、添加、補足、添加などを使い、型を崩して、型を離れて書く方法も詳細に説明されてしています。
ここまでがこの本の内容です。
作文は学校の定期テストや入試において欠かすことはできません。
この本は、文章をどう構成したら良いのか、どうしたら内容が膨らむのか、指定された字数を満たすには文章をどう工夫すれば良いのか、など、 基本的な形式(型)を使用して、 段階を追って文章力を身につけていく方法が書かれています。
日記や読書感想文や小論文など様々な場面で学生でなくても、大人でも役立つ方法だと思います。
この本では、どれぐらいのレベルの問題を解けるようになるのか、章ごとに分けて目的をもって書かれています。
読み進めていくごとに書けるようになる文章のレベルが上がっていて、順序よく文章力をつけることができるように書かれていると思います。
また、ある一つのことを軸にして話が繰り返し、展開されていて、筆者の伝えたいことがより簡単に理解できます。
また、この〝ふくしま式200字メソッド〟は、短い文章を例に挙げた説明から始まり、長い文章を書けるようになるまで、たった一つの「型」を応用することによって様々な場面に使えると説明されています。
この本で説明されている、「型」を頭の隅に置くだけでも、効果があるのではないかと思います。
スポンサーリンク
