「本当の国語力」が驚くほど伸びる本―偏差値20アップは当たり前! 福嶋隆史
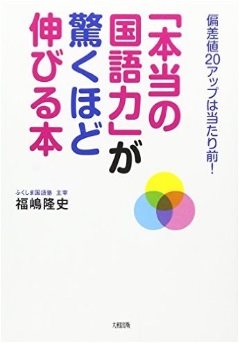
この本は、国語塾を経営されている福嶋隆史(ふくしまたかし)さんが「本当の国語力」の身につけ方について説いた最初の本になります。
対象は小学生を持つ親御さんに向けに、我が子に国語力を指導できるように書かれた本ですが、中学生、高校生、大人までも、参考になる本だと思います。
中学生以上になると、自分自身で読んで勉強できると思います。
スポンサーリンク
以下、この本の内容紹介です。
本当の国語力とは、内容を味わうことではなく、形式(理論的思考力)を身につけることだ。
形式を身につけていないと内容を十分に味わうことができない。
形式を身につければ内容を十分に味わうことができる。
国語は、何を読むかではなく、『どう読むか』、です。
国語は、何を書くかではなく、『どう書くか』、です。
読む方法、書く方法が重要です。
つまりは、形式を身につけることです。
形式を身につけるために必要な力を、「言いかえる力」、「くらべる力」、「たどる力」の3つのポイントに分けて説明しています。
この3つの力、これこそが国語力です。
世間では、国語力を、話す力、聞く力、書く力、読む力、などと定義しているようなところがありますが、これは野球力、バスケ力、サッカー力と言っているようなもので、実態がみえません。
一方、先に示した3つの力はたとえるなら、走る力、投げる力、跳ぶ力といった原初的技能を示しており、その実態が見えます。
それは、言わば形ある国語です。
優れたコーチは、パス練習、ドリブル練習、シュート練習などを行わせ、いつの間にか選手に力がついていた、という状態を生み出します。
それら一つのひとつの「技術・形式」つまり形式を身につければ、選手はそれらの力を総合的に発揮しながら優勝を手にすることができます。
国語力も同様に、形式を身につけることにより、本当の国語力が身に付きます。
スポンサーリンク
以下、3つの力の説明です。
「言いかえる力」
これは、一見バラバラに見えるもののなかに「共通点」を見つけ出し整理する力です。
「つまり」、「たとえば」、などを使用して抽象化(要約)/具体化を切り替えて説します。
どんな文章も、基本的には抽象と具体の間を往復しながら書かれています。
抽象的に言いかえる代表的な接続詞は「つまり」です。
具体的に言いかえる代表的な接続詞は「たとえば」です。
例:
・抽象化・・・「みかん、ぶどう、バナナ」つまり「果物」
・具体化・・・「果物」たとえば「みかん、ぶどう、バナナ」
この2つのシンプルな言葉が「言いかえる力」の重要なカギとなります。
近い枠組みで抽象化/具体化を言いかえることの重要性を「マトリョーシカ方式」で分かりやすく説明されています。
この言いかえる力こそが読解問題で試される本質である。
「くらべる力」
これは、一見バラバラに見えるもののなかに「対比関係」を見つけ出し、整理する力です。
「しかし」、「でも」、などを使い対比的な言葉をつづけて意味を強調させます。
世の中出来事など、ほとんどのことは、何かと比べて、大きいとか小さいとかと表現します。
対比にも、以下の2種類がある
ワンセット:朝と昼、晴れと曇り、など複数の組み合わせがあるもの
正反対:暑いと寒い、大と小、明と暗など、これしかないという絶対対比
この比べる力で文章の訴えかえるスピードとパワー激変させます。
「たどる力」
これは、一見バラバラに見えるもののなかに「結びつき」を見つけ出し、整理する力です。
「だから」、「そのため」、などを使い、正しい因果関係(原因と結果の関係)の言葉をつづけて分かりやすくあるいは納得のできる説得力の高い表現をします。
例
——————————-
この公園にはごみ箱があった。
だから、ごみ箱を撤去した。
——————————-
強引で納得できない。
——————————-
この公園にはごみ箱があった。
そのため、カラスがごみ箱を荒らし始め、公園が毎朝よごされるようになった。
だから、ごみ箱を撤去した。
——————————-
説得力が生まれました。
この場合の注意点としては、「そのため」、の次にはいる文の客観性があるかないかによって正しい因果関係になっているかかどうかが決まります。
客観性とは、10人中、8人以上が納得できる内容になります。
10人中、8人以上が納得できる内容だと「だから」、「そのため」が成立します。
話す力、聞く力、書く力、読む力の中にはこの「言いかえる力」、「くらべる力」、「たどる力」の3つの力が全て含まれています。
この3つの力は、国語力を伸ばすだけにとどまりません。
他の教科も文章で書いて説明されているような問題が出題されているため、他の教科の点数も上がって行くという結果になります。
また、この3つの力の使い方に学年の差はありません。
ここまでがこの本の内容です。
私が、この本を読んだ感想は、要点がきちんとまとまっていてシンプルで、また図を用いて順序よく説明してあるので内容がすんなりと頭に入ってきました。
教える立場の人に向けて書かれた文章で、教え方を理解しやすく、また言葉のニュアンスの少しの違いを細かく説明しているので、子どもに教える時でも迷うことなく教えることができるのではないかと思います。
子どもの「本当の国語力」を身につけるために。算数や理科の問題を解く力は伸びていくのに、国語力はなかなか伸びない。そんな悩みをもっている方は多いのではと思います。
センスの科目だと思われがちな国語を、論理的思考の観点からとらえていて、国語力とは何かということを改めて考えさせられる本だと思います。
また、テストでも確実に点数をとるための考え方だと思います。
国語専門の塾講師が教える「本当の国語力」の伸ばし方。試してみる価値はあると思います。
スポンサーリンク
